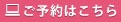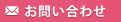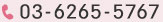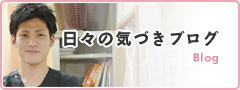首が普通に動くことは、普通?
誰かに呼ばれて、振り返る。
興味があるモノの方向を向く。
顔を向けたい方向があれば、その方向に顔を向けるように首を動かす。
普通に出来ていた事が、普通に出来なくなると、とても不便ですし、
何故!?ってなります。
そこに加えて痛みなどが伴えば、この痛みは一体なんなんだ?と、不安も伴うかもしれません。
これが、算数の計算だとしたら。
途中の式を見直したりしたら、やり方が間違っていたことは容易にわかると思います。
小学生の頃に教わったであろう、計算のプロセスがあるからですね。
ただ、首の動きは、特別に誰かに教わったものでもないので、その途中式がどうなっているかが、わからない。というか、知る必要もなかったんですね。
更に言えば、その首の動きという途中式を知ったところで、全て意識的に出来るほど、単純なものでもありません。
何故、単純ではないかと言えば、何層にも複雑にすることで、お互いに助け合って、そう簡単には、動けなくなったり、痛くなったりしないようにしているのです。
裏を返せば、痛くなったり、動かなくなってしまった時には、
なかなか複雑に原因があって、それ相応の期間も経ている事になります。
このような背景を持った、首の痛みや、動かないといった症状と向き合う時に、
理屈としての、首の運動の仕組みも大切ですが、
人の運動には、複数の運動が同時に行われながら、滑らかに動くという特性があります。
この滑らかな動きというのは、反復しながら覚える一面と、動かす際に、どんな目的で、何を意識するかという、形があるようでない側面もあるため、
原因が明確でない、というか、ご本人の自覚として、何故、現状に至ったのかが明確にならない場合が多くあります。
病院に行って検査をしたけれど、それほど問題があるわけでもないのに、何故か、年に数回痛みがやってきたり、慢性的に動きが良くない、ある方向に動かすと痛みが伴うといったような、ご相談を受けることがあります。
このような場合、その動きを診させて頂くと、
“してほしい動作”を無意識にしなくなっている or 出来なくなっている
“してほしくない動作(≒身体に負担のかかる動き)”を無意識にするようになっている
といった、痛くなる動作、動かしにくい動作が、癖になって、それが“普通”になってしまっています。
補助的に誘導すると、痛みが軽減するけど、
補助なしで、ご自身で動かすと、やっぱり痛い。
この癖やパターンを修正する。
算数の計算で言う、途中式をもう一度、身体に教える必要があります。
小脳 と 巧緻性(こうちせい)
動きの滑らかさ・・・・・専門的に言うと『巧緻性(こうちせい)』とも言います。
一つ一つの運動が上手く結び付いて、滑らかなで自然な運動を創るのですが、
それを司っているのが『小脳』と呼ばれる部分になります。
生理学的には、反復することによって、小脳の働きによって、巧緻性が増していき、無意識に自然で円滑な運動が行えるようになる。
と書いてあった気がします。
ただ、これには少し足りない部分があると思うんです。
恐らく、反復することで、巧緻性が増すのは確かだと思います。
ただ、同じ回数反復した、数人の人が同じように、巧緻性が増すかというとそうでもないときがあります。
もちろん、年齢や体格などの問題も多少はあるでしょう。
もうひとつ、要素として大きいのが、『意図』・『意思』・『目的』・『目標』という部分が明確かどうか、この部分でも大きく差が出てくるんだと思います。
目標や目的は明確に持っているけど、それが、運動や動作や表現、目の前の現実に反映されてこない場合、
その目標のイメージや意図の設定が、少しずれている場合もあります。
ボタンの掛け間違えのように、最初は気がつかないくらいのズレでも、どんどん時間や回数を重ねるごとに歪みが大きくなり、結果として、襟がすごいズレていた・・・・なんてこともありますよね。
脳でイメージされた、『こうしたい』 『こんなふうに動かす』 という、まだ漠然とした動作の指令が、首を伝わって、背骨の中を通り、あらゆる部分に命令を届けています。
その命令の通り道が、歪んでいて、正確に伝わらないと、動作もうまくいきません。
命令の発信元である、脳が疲れちゃっていたり、頭の骨の歪みによって、うまく情報を発信できなくなってしまっていても、結果として、動作はうまくいきません。
指令はちゃんと届いているけど、指令を受けた部分が、硬かったり、歪みが起きていても、
その指令通りに動かせません。
『こうしたい』 『こうゆうふうに動かす』 って思っている反面、
『実はあんまりこうしくないなぁ』 『こうゆうふうに動かすの好きじゃな~い』
って、指令がハーフ&ハーフでお届けされても、動作がうまくいかないときがあります。
指令を届ける役割の神経も、その道の途中に、山あり谷ありで、それを越える為には、栄養が必要です。
栄養が足りなくても、指令が上手く伝わらない。。。。
指令を発信して、届けて、動作をするって、大変。
文字で見ると大変。
理論上の原因を探れば山ほどある。
でも、そんな大変な事を、身体はいつも陰ながらせっせとやっています。
そんな身体が悲鳴を上げたとき、
どうしたのですか?
それは大変でしたね。お察しいたします。
大丈夫ですよ。少し休みましょう。
あなたの今までの頑張りの想いは、きっと届きます。
そんなに頑張らなくても大丈夫です。今のままでも十分ですよ。
と、細胞に働きかける事で、またいつもどおり動いてくれるようになります。
ご自身の身体から発信される、『痛み』や『不調』は、身体からの何かしらのメッセージです。
ただ、治ればいい、動くようになればいいのではなく、
ご自身の身体が何を伝えたいのかを振り返る良い機会でもあります。
そんな身体との対話のお手伝いが少しでもできればと思います。